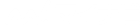【WebX 2025】日本円ステーブルコイン第一号 詳細と今後の展望

この記事の目次

日本円ステーブルコイン第一号が誕生!
2025年8月、WEBX2025にて開催されたセッション
「日本円ステーブルコイン第一号 詳細と今後の展望」の内容を時系列に沿ってまとめました。
モデレーターはCoinDesk JAPANの神本 侑季氏、登壇者はJPYC株式会社 代表取締役の岡部 典孝氏です。
2024年6月、JPYC株式会社が資金移動業者として日本円建てステーブルコインの発行ライセンスを取得。
日本初の正式な発行体として、CoinDesk JAPANなどのメディアやSNSでも大きな話題となりました。
ライセンス取得までの2年間と今後の展開
2019年の会社設立、2020年の実証実験を経て、2023年の改正資金決済法の施行を機に申請を行いました。
改正日当日に「第1号を狙う」と金融庁に直接連絡したほどのスピード感で、2年の準備期間を経て取得に成功。
今後は信託銀行型や外貨建て、外部ステーブルコインの仲介業務にも注力するとのことです。
スキームの違いとユースケース:信託型 vs 資金移動型
- 資金移動業者型(JPYC):自由度の高い流通が可能
- 信託型(JPYCトラスト):Progmat社と発行予定のステーブルコイン。大企業向けで信頼性重視。POS決済や法人活用に強み
第二種資金移動業の場合は1送金額の上限(100万円)はあるため大口の資金は使いづらいですが、「第1種資金移動業」取得で将来的には拡大可能です。
普及はどこから始まるのか?
初期ユーザーはCrypto投資家や機関投資家、ファミリーオフィスなど高リテラシー層です。
今後は電算システム等の提携を通じて、一般利用への拡張(コンビニやEC等)を目指しています。
会計・税務面の優位性:暗号資産との違い
- 会計上は現預金扱いが可能
- 税務処理が明快でNFTやデジタル取引の会計が圧倒的に簡易化
- 暗号資産と比較しても、ビジネス導入が現実的
ステーブルコインが切り開く日本経済の未来
- 日本のM2(マネーサプライ量)は1200兆円強。ドルのステーブルコインがM2の1.5%(18兆円)くらいでこれが10%(120兆円)になると言われている
- JPYCはまずは5年で85兆円の発行額を目指す
- AIエージェント経済やオンチェーン決済の中核へ
- 国際的な通貨競争で日本円の存在感を維持する鍵になると思われる
「AIが使えるお金」という視点
- 人間に加え、AIやロボットにも使える設計
- AIが主導する経済圏における決済インフラとしての役割が大きい
- デジタル決済の未来は、人的利用だけでなくプログラマブル化された世界の中心に
他社ステーブルコインとの「共存戦略」
JPYCは、銀行・信託・外貨発行体と相互接続可能な立場を確立しています。
あらゆるステーブルコインを「両替・仲介」できるプラットフォームとして拡大を図っています。
ユースケースは無限大
- 定期支払い(例:人材派遣・副業報酬)
- AIエージェントによる自動決済
- NFT売買や投げ銭サービス
- スタートアップの資金調達(社債・株式)
特に「JPYCで資金調達」が、法改正によって現実味を帯びてきています。
今後1〜3年の展望
- StripeのようなSaaS型ステーブル決済プロバイダが登場
- 既存金融資産(株・社債・国債)のトークン化
- 「オンチェーン化された経済」の最後のピース=「決済」が埋まる未来へ→オンチェーン化が加速されるのでは
全体的な感想
今回のセッションを通じて、ステーブルコインが単なる「決済手段の一つ」ではなく、デジタル経済やAI時代における基幹インフラになりうることを実感しました。
特に人材関連の報酬支払いや副業報酬、海外人材とのグローバルな金銭授受の文脈では、JPYCのような日本円ステーブルコインが果たす役割は確実に大きくなるのではないかと感じました。
マイナビという人材領域の企業に身を置く者としては、報酬の透明化・自動化・即時化といったトレンドに備え、こうした技術に早期からキャッチアップしておく必要があると強く感じました。
※本記事は2025年09月時点の情報です。