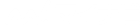新人研修って何をしたの?4か月のリアルを公開(2025年度新人研修)

この記事の目次
はじめまして!2025年度新卒のW.Mです。
4月に入社してから4か月間受けてきた研修が終わりを迎えました。
研修期間中は非常に濃い4か月間を過ごしました。しかし、どのようなことを学んだのかは、研修担当の方々や日報を担当してくださった先輩社員以外の方々はご存じないかと思います。
そこで私たちがこの4か月間何を学んできたのかについて、受講した新卒の立場から皆様へご紹介させていただきます。
実際に研修で使用した教材や研修の一環で作成した成果物を参考資料として添付しておりますので、ご覧いただき研修の雰囲気・内容を掴んでいただけますと幸いです。
研修の流れ

新入社員・デジ戦研修(~4/18)
※デジ戦研修:デジタルテクノロジー戦略本部研修
入社式を終え、まず最初に受けた研修は新入社員研修・デジ戦研修です。
新入社員研修
こちらは職種関係なく、新卒共通で行ったものです。ビジネスマインド、ビジネスマナー、自律と主体性について学びました。
例えば、、、
- 会社の信用
- 職場でのコミュニケーション
- 文書作成のポイント
- 挨拶・身だしなみ・敬語
- 名刺交換
- マインドセット
- タイムマネジメント
など、社会人として当然備えておくべきである基本を学びました。
特に名刺交換はその後行った営業同行ですぐに実践できました。
こちらの研修はグループワークも多く、入社したてで緊張していましたが、同期たちと話すことで緊張もほぐれ仲も深まりました。
デジ戦研修
デジ戦研修では、本部長登壇、統括本部紹介、職種紹介、2年目社員座談会が行われました。
この研修によって「デジ戦はどんな働きをしているのか?」について理解が深まりました。
入社前からどのような部署があるか伺っていましたが、具体的に何をしているか把握できていませんでした。お話を聞いたことで、各統括部・職種の役割・ミッションを知り、配属後の仕事の解像度が上がりました。
また、業務内容だけでなく、社会人としての在り方についての学びもありました。
最後にくださった新卒へのメッセージで特に私が印象に残っていることが「挑戦」というワードです。
責任が増えるにつれミスができなくなり、挑戦ができなくなるため、若いうちの立場に積極的に挑戦した方が良いというお話をお聞きしました。
また、失敗を恐れずに挑戦すべきとおっしゃっていた方も多くいらっしゃいました。
ただ失敗だけで終わらせず、なぜ失敗したか、その後どう行動するかが重要だということも学びました。
配属後はいただいたメッセージを胸に刻み、一生懸命頑張っていきたいと思います!
IT/Web研修(~5/30)
IT/Web研修は、Givery社の方に研修を担当していただきました。
▼この研修ではIT知識・言語などの基本を一通り学びました。

研修当初は、各自でワークを進めていましたが、Pythonに入ってから、初学者と経験者でチームとなって学習を進めるようになったことで、初学者が分からない部分をすぐに解決できるようになりました。
この研修では、ほとんどの単元をハンズオンで学習を進めていきました。
できるようにならないと次に進めないため、しっかり知識を定着させることができました。
▼Pythonの学習教材の一部

▼複数の単元を学習後の理解度チェック(SQL)

参考資料:研修資料の一部
セキュリティ 基礎講座 知識編 セキュリティ技術評価.pdf
データベース 入門講座 実践編_複数テーブルの結合.pdf
Webアプリ開発(バックエンド, Python Django) 応用講座_全体概要.pdf
職種別研修(~6/9)
IT職、Web職、デザイナー、データサイエンティストの4職種に分かれて5日間職種別研修を受けました。
私が受けたIT職研修以外の研修内容についても、同じく新卒社員に聞いてみました。
IT職
ウォーターフォール開発講座
地方都市の観光業の復活を支援するためのITソリューションの提案を、
要求・要件定義→基本設計→詳細設計→単体テスト→統合・総合テストという流れで3人1チームで行いました。
詳細設計に入る前には、これまでのチームと変更し、他のチームが作ってきたものの詳細設計・テストを行ったことで、より実際の業務に近い形の研修になったと感じています。
クラスやオブジェクトの概念理解が難しく、UMLの作成に苦戦した人が多かったため、当初の予定よりも詳細設計の研修日数が1日伸びました。しかし、そのおかげで理解が曖昧だった点が解消でき、学びが深まりました。
5日間という短い時間で上流から下流まで行うのは難しく感じましたが、実際に手を動かしながら一通り経験したことで、ウォーターフォール開発がどのようなプロセスで何を行うかについてしっかりと理解できました。
参考資料:ウォーターフォール研修提出資料の一部(チーム6)
Team6_要求定義・要件定義.pdf
詳細設計_Team6.pdf
Web職
オリジナルステーショナリーブランドのマーケティング施策
Web職は、職種別研修が始まった初日にデザイナーと合同チームで決めたオリジナルステーショナリーブランドを売るためのマーケティング施策等を考えました。
- 他社商品分析
- 新商品案出し、訴求法検討
- 「半年で売り上げを安定軌道に」というゴールからKPIツリー作成
- 6か月間のマーケティングロードマップ作成
- 予算配分と期待効果のシミュレーション
これらをWeb職の研修で行い、最終的にはデザイナー職と合同で「ステーショナリーブランドの企画」を行いました。どのように売り出していくのかについて真剣に向き合い、売り上げ数値の整合性・採算性についてもアドバイスをいただけました。
多職種との連携をとることでマーケターとして必要なコミュニケーションの取り方を学び、その後の開発演習にも大いに役立つ研修でした。
(M.Y)
デザイナー
「わたしが知っている神ECサイト・悪ECサイト」
普段自分が利用しているECサイトやアプリなどを振り返り、「わたしが知っている神ECサイト・悪ECサイト」と称してデザイナー間で共有を行いました。
使いやすいと感じるUIと使いにくいと感じるUIを紹介し合ったことで、個々の感じ方の違いを知ることができたり、UI/UXに対する理解度を上げることもできました。
ここで得た知識や感性を活かして、最終的にはマーケティング職と合同で「ステーショナリーブランドの企画」と「ECサイトのデザイン」を行いました。他職種との連携の取り方や短期間でデザインを行うことを経験することができ、後の開発演習の土台にもなった研修でした。
(K.N)
参考資料:Web職・デザイナー共同の最終発表資料(チーム1)
チーム1_オリジナル商品企画.pdf
データサイエンティスト
台東区の観光アンケートを分析して、観光業者が収益を上げるための施策提案資料の作成と発表
3名という少ない人数で、講師もいなかったため、大変な面もありましたが、他の研修ではできないDSとしての学びを得ることができました。
研修を受けて、施策立案のグループワークを通じて、分析力だけでなく、課題設定力やコミュニケーション力など、複合的なスキルが求められることを実感しました。
自分自身の思考や関わり方を見つめ直す良い機会となり、非常に有意義な経験でした。
(I.Y)
参考資料:DS提案資料
DS研修_プロジェクト.pdf
開発演習(~7/17)
職種別研修を終え、そこから約1か月ほど開発演習を行いました。
開発演習では、就職・バイト・研修の3つのサービスで各3チームずつで、各職種の強みを発揮しながらチーム開発を行いました。
各チーム、ピボットやエラーなど様々な壁にぶつかりながらも、自分たちが考案した施策が最大限よくなるように試行錯誤し、完走いたしました。
▼成果報告会の様子

また、先輩社員にも巡回での相談やレビューに参加してくださる中で、多くのアドバイスをいただくことができました。
開発演習の各職種の体験記について、詳しくはこちらで25新卒が作成しているので、よろしければご覧ください。↓
新人たちが挑んだチーム開発の舞台裏(2025年度新人研修) | マイナビエンジニアブログ
内製研修(~7/30)
3日間でマーケティング研修、デザイン研修、DS研修が行われました。
それぞれの職種の先輩方が研修を行ってくださり、IT職としてはなかなかできない貴重な経験ができました。
マーケティング研修
LPやリスティング広告といった広告の種類名など、様々なマーケティングに関する用語を学びました。
また、午後には「マイナビジョブサーチを広告費300万円で”選ばれる状態”にしろ!」というテーマで、マーケティング戦略提案資料、広告チャネル配分表、LP企画案、稟議書の作成をチームで行いました。
デザイン研修
前日のマーケティング研修で考えたLP企画案から、LPのデザインの作成を行いました。
多くのチームがマーケター・デザイナーがともにおらず、話し合いながら形にできるように試行錯誤しました。
DS研修
午前のグループワークでは、タイタニック号の乗客データから乗客の生存率の仮説を立て、検証を行いました。
午後にはAIツールのアイデアソンを行いました。AIを使用するという以外は制限がなく、チームによってさまざまなプロダクト・サービスの発表をしました。
振り返り
上記の研修以外にも、営業同行やAWS外部研修、スライドデザイン研修など、多くの貴重な経験をさせていただきました。
研修全体を通して、配属後の解像度の向上・基礎となる知識の形成・チーム開発の経験を得ることができました。そして、同期の仲もとても深まりました。
ここまでお伝えした内容は私自身が感じた学びが中心となってしまいましたが、新卒社員全員がこれまでの経験、研修中のチームや開発演習のサービスなどが異なり、それぞれ違った学びを研修で得ました。
最後に、新人研修に関わってくださった皆さま、教育担当の方々、本当にありがとうございました。
研修で学んだすべてを糧に、配属後も尽力していきます。
※本記事は2025年09月時点の情報です。