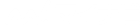【社員インタビュー】AI技術で課題解決に挑む!現役エンジニア2名が語る組織もツールも一から作り上げていくやりがい

この記事の目次

はじめに
デジタルテクノロジー戦略本部の中でも「AI」を使った業務改善を企画・提案するAI戦略室。事業部やサービスにコミットしたAIツールを日々開発している2名に「AI戦略室で働く魅力」についてお話を伺います。
プロフィール
M.Yさん
所属:デジタルテクノロジー戦略本部 AI戦略室 AIソリューション部 AIソリューション2課
マイナビに入社する前はSESとして受注開発をメインに、自動車や小売データの基盤構築やスマートフォンアプリの開発・運用・保守を担当。管理職の経験はありませんでしたが、チーム単位での売り上げ・タスク・スケジュール管理も経験しました。
2023年にマイナビへ入社し、2024年10月にAI戦略室の立ち上げと共にマネージャーに就任。
現在は、課長としてメンバーをまとめる役目も担っています。
Y.Nさん
所属:デジタルテクノロジー戦略本部 AI戦略室 AIソリューション部 AIソリューション3課
大学で電子情報工学を学び、2021年4月に新卒で入社しました。
現在は、音声処理に関する検証やAIを使ったAPI開発に携わっています。
M.Yさん

AI活用を次のステージへ
マイナビに入社したきっかけを聞かせてください。
「AIを使ったシステム開発、データ活用をしてみたい」と考えていたタイミングで、ちょうどマイナビで働いている方からお話を聞く機会がありました。マイナビの安定した労働環境も決め手のひとつです。
入社したときはAIシステム部への配属でしたが、2024年10月にAI戦略室という名称に変わりました。
その時期は「もっと会社の中でAIの活用を推進しよう」というタイミングでした。
もちろん、AIを使った課題解決には以前から取り組んでいたのですが、もっと営業の売り上げや制作現場のコスト管理に踏み込んだ活用をしていこうという流れに変わったと感じています。
ちょうどこの時期にマネージャーに就任しました。
求人の『出会い』をAIで最適化
現在関わっているプロジェクトを教えてください。
ウェブ・スマートフォンアプリ『マイナビジョブサーチ』の求人レコメンドの開発や、求人原稿の生成・内容チェック、求人を載せるための基準を策定する際の時間を削減できるようなシステム、アプリケーションの開発などを行っています。
特に『マイナビジョブサーチ』のレコメンドエンジンの開発に注力していて、ユーザーとのマッチング精度を向上させる必要があるなどの課題に向き合っています。
現場と向き合い、売り上げにコミットするAI活用
お仕事のやりがいはどのようなところでしょうか?
受注開発でクライアント企業から依頼されたものを期日通りにリリースすることに注力していた前職に比べ、より現場やサービス事業部の方々と向き合う時間が増えたと感じています。
「より売り上げにコミットしていくには?」と検討していくことは前職ではあまり経験がない領域だったので、特にやりがいを感じます。
仲間と乗り越えたAI戦略室の転機
マネージャーになってから印象深いエピソードはありますか?
組織の変革期と部署のメンバーの退職が重なって大変でした。
ちょうど入社3年目、4年目の技術力がついてきた人材が抜けてしまい、課のメンバーにはかなり頑張ってもらったと感じています。
私たちの部署はAIやデータサイエンスの領域でかなり専門性が必要になってくるので、各メンバーに技術や知識の向上を図ってもらいました。
初めてマネージャーという立場になったので、右も左もわからず、上司には一から丁寧に教えていただきました。
今もたくさんの人に支えてもらっていることに感謝しています。
日進月歩で進化するAIやデータサイエンスの領域では、知識のアップデートが必要です。
エンジニアの知識はもちろんですが、マネージャーとしても各メンバーを導くための専門知識が必要になってくるので、日々インプットを続けています。
AIで事業を進化させる挑戦
AI戦略室で働く魅力とは何でしょうか?
AI戦略室は、まだまだ伸びしろがあります。
「一から作っていく」という雰囲気の中で、自社の事業部全体をAI技術を活用して成熟させていく体験は他では得難い魅力だと思います。
私はAI分野が専門ではなかったので今もかなり苦労していますが、そこが私が求めていた「新たな領域へのチャレンジ」なので、毎日充実しています。
他のテック企業を超えるAI組織をつくる
今後の目標を教えてください。
3年後や5年後を見据え、他のテック企業にも負けない、むしろ追い越すような組織の基盤づくりや技術力の向上を目標にしています。
Y.Nさん

音声AIツール開発の最前線
現在関わっているプロジェクトについて教えてください。
機械学習エンジニアとして、議事録を自動で生成してくれるAIシステム『GIJILOG』や高校生向けの面接練習AIアプリケーション『AI-m』の開発に携わっています。
音声の前処理や音声特化型AIモデルに音声を入力し、適切なアウトプットを得て、アプリケーションへつなげる一連のフローをAPIとして提供しています。
この2つのプロジェクトは、ユーザー(人間)が話した音声をテキストに変換する音声処理技術を活用しています。
私は学生の頃からこの技術を研究してきたので、知識を活かしながら、日々の業務と向き合っています。
リアルな声が届く現場密着型のAI開発
プロジェクトでのやりがいについて聞かせてください。
AIという最新技術を常にキャッチアップし、事業部の課題解決にどのように活かせるかをチームで協議し、狙い通りに解決できたときにやりがいを感じます。
技術向上への学習意欲を上げるために、部署内の有志が集まって勉強会も開催していて、メンバーが興味を持った事例やテーマを共有しています。
自分たちが手掛けた技術が本当に実用的なのかを検証した上で、良い結果ならそのまま導入につなげます。
また、悪い結果でも「どう改善していくか」をチームで考察してプロジェクトを進めていくので、成果に対する手応えをダイレクトに感じています。
私たちは社内の現場や事業部のすごく近いところで開発をしているので、ユーザーからのリアルな声がすぐ届きます。
「生の意見が直接聞ける」という点は、社内開発だからこそのやりがいだと思います。
前例ゼロからの挑戦
お仕事をするなかで、うまくいかずに苦労したことはありますか?
私は音声を扱う業務に携わっているのですが、社内で音声に関するAI技術の前例や知見がなく、音声を使ったシステムの提供の仕組みやフォーマットも定まっていませんでした。
そのため、運用体制を一から考えて進める必要があり、苦労しました。
ただ、それが自身の技術向上につながったと思います。
後進育成と成果の両立が自身の成長に
入社5年目とのことですが、気持ちの変化やお仕事の向き合い方で変化はありましたか?
一番の変化は、後進育成の比重が高くなったことです。
タスクを遂行する立場から、タスクを細分化してメンバーに配分し、成長の機会を提供する役目へ変わりました。
それに合わせて、人的・金銭的コストと全体のリスクなどを意識できるようになったと感じています。
自分の視座が上がったので、「もっと良い方法があるのではないか」とプロジェクト全体を俯瞰して考えるようになりました。
その点は自分の成長を感じているところです。
音声でつなぐ対話型AIの未来
今後の目標を教えてください。
AIを利用した事業成長や業務負荷の軽減に貢献できるプロダクトを継続的に生み出していきたいと思っています。
議事録生成などは、まさに会議が終わった後の手間を省けるツールなので、そこに重きを置いていきたいです。
学生時代から「音声は誰にとっても使いやすいインターフェース」だと思って音声処理を扱っていたので、ゆくゆくはそこに絡めて、社内・toCに向けた対話型AIツールの構築も進めていきたいと考えています。
現在、「営業のロールプレイができる対話型AI」のプロジェクトも進行中です。
このような現場の生産性向上に直結するような価値をこれからも提供し続けていきます。

※本記事は2025年11月時点の情報です。